
本記事は「雑阿含経巻第35-990」の内容をもとに作りました。
どっちが優れているのか?

アーナンダさん。あなたのお師匠さんであるお釈迦さんは、本当にできた方なのですか? どのように真理を知ったのでしょう?
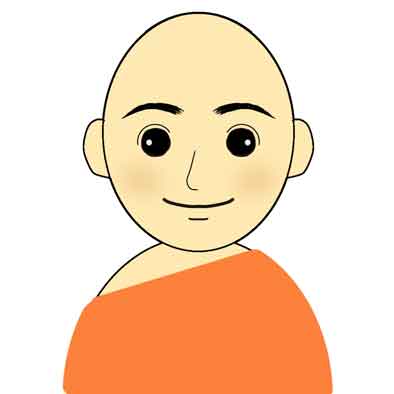
どういう事でしょう? 質問の意図が分からないのですが。

私には亡くなった父がいました。出家して町から離れ、ある人の弟子として生きました。師のを教えに厳格に随い、戒律を守っていた人でした。
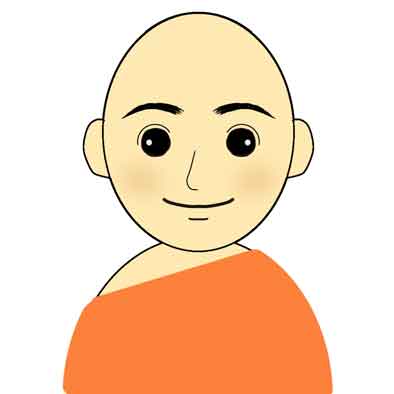
お父上は真面目な方だったのですね。

はい。ただその真面目さゆえに、周りが見えず、人に騙される事もありました。決して頭が良いとは言えませんでした。
そんな父は、師の言われた通りに戒律を守り、清く正しい人物であろうとした人でした。
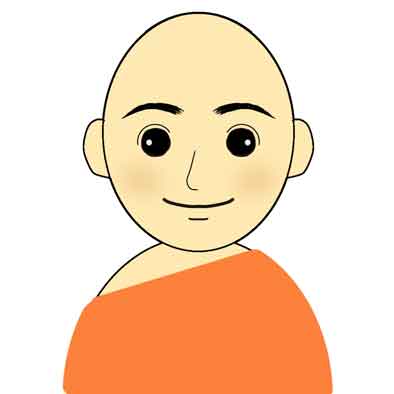
そうですか。立派な方だったのですね。

さすが、師弟ですね。
あなたも師匠であるお釈迦さんも同じように言っていましたよ。

ですが、その父には兄弟がいます。私にとっては叔父にあたりますが、この叔父が亡くなった時、同じように言っていたんですよ。
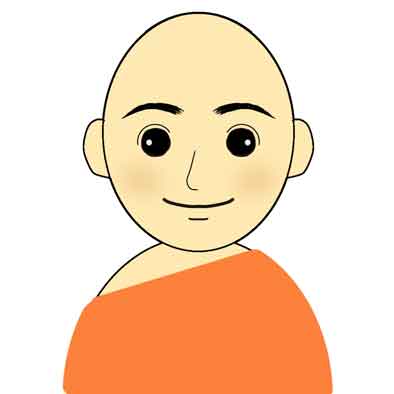
と、言いますと?

叔父は父と違い、とても頭のよい人でした。周りが良く見えていて、聡明な人だと私は思います。
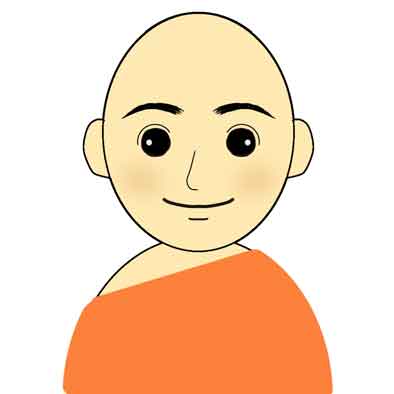
とても賢い人だったのですね。

はい。ただ父のように出家する事はなく、ましてや戒律を守るような生活はしていません。それでも父に負けず劣らず、清く正しい人物であろうとした人でした。
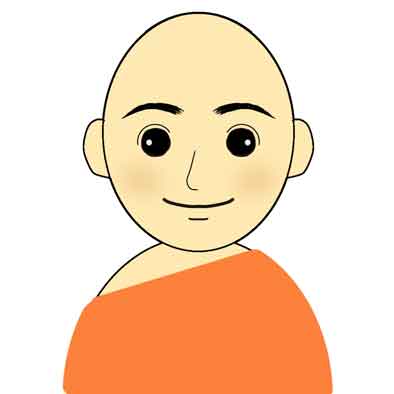
そうですか。立派な人だったのですね。

やはり、あなたもそう言うのですね。父と叔父、両方とも立派だと申しますが、二人は全然タイプが違います。父と叔父が同一の評価というのはおかしいかと思いますけど。
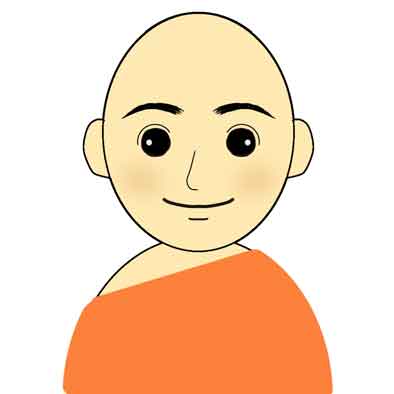
おかしいとは、どういう意味でしょうか?

父は真面目に戒律を守っていましたが、賢くはなかった。一方叔父は賢かったが、戒律を守ってこなかった。

戒律を守る方が優れているのか、賢い方が優れているのか、一体どっちなのでしょうか?
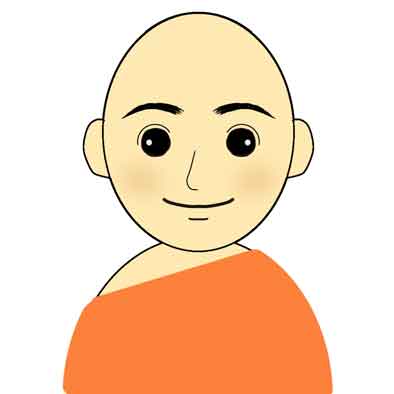
ちょっと待ってください。どうしてそんな話になるのですか?

要するに戒律を守って厳格に修行する事が良いのか、それとも修行なんてしなくても、賢く聡明である方が良いのか。「どっちなんだい!?」という話です。一体どっちの方が真理に近いのでしょうか?
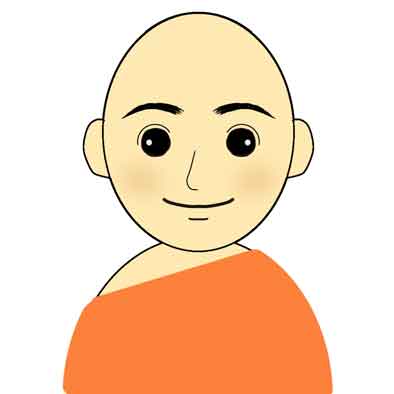
確かにお父上と叔父上に違いはありますが、優劣があるというもでもなく……

どっちが上でどっちが下なんですか?
同じではなく違いがあると言いましたよね?
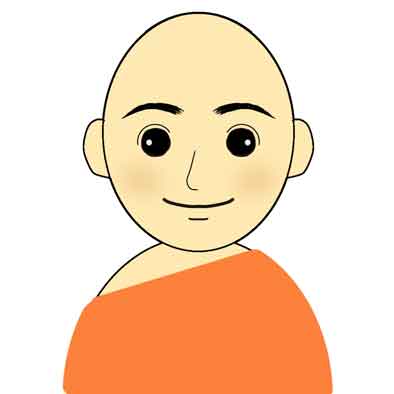
いえ、上手く答えられないのですが……

ほら、答えられませんね。
比べられない
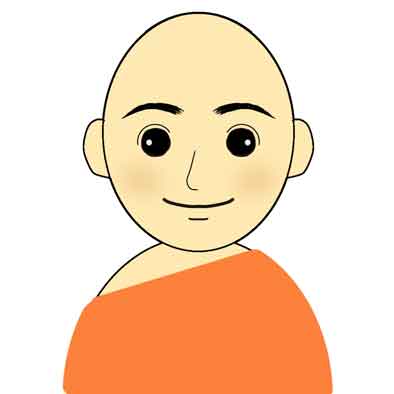
と、いうことがありまして……。
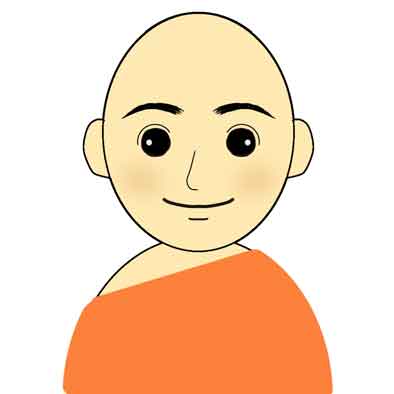
師匠、私は何と答えたらよろしかったのでしょうか?

そのように、どっちが優れているとか、どっちが劣っているとか、数字で判断するように思い計るのは、それこそ、苦しい事ですよ。何の役にも立たない事です。

例えば、父親の方は「自分が賢くない」と自分自身のことを見つめていた方でした。

確かに、そのお父さんも偉いよね。

どうして?

頭が悪いというのは、ある意味、自分の欠点じゃない。普通は欠点と言ったら嫌でしょう。認めたくないし、見たくない。

ああ。でもそのお父さんは、そういう自分の欠点含めて、自分を見つめていたんだね。

そうですね。自らの欠点を認め、向き合うというのは、当たり前の事のようで、そう簡単にできるものではありません。

父親は自らの欠点と向き合っていたからこそ、己を過信することなく、師(先人)の指導に随い、戒律をよく守っていたのです。

それはそれで立派な事ですね。

はい。自ら一歩退いてよく自己を見ていた、物事を見ていた人だと私は感じました。

一方、兄弟である叔父もまた、戒律に固執することなく、自己を見つめ、そして周りとよく観ていた方でした。

その叔父も偉いですね。

どうして?

戒律ってある意味「ルール」じゃない?

確かに、「律」には他者との「ルール」という意味があるね。

ルールに固執すると、融通がきかなくなったり、相手の意見がきけなくなったりすることあるでしょう?
自分の方がルール的に正しいからって固執してしまうことが。

ああ、そういったルールに固執することもまた注意しないといけないね。

ルールに固執する。正しさに固執すると、自己のルールや正しさに陶酔してしまうわけなじゃない?

そういうの自己陶酔というのかな。

うん。自己陶酔したら、自分の事見えなくなる。でも叔父さんはそんな事なかったのでしょう。

そうですね。叔父もまた戒律を学んでいましたが、その戒律(ルール)に執らわれないよう、よく自己を見つめ、物事をよく見ていた方でした。

それはそれで立派な人ですよね。

はい。戒律(ルール)という型にはまらず、よく戒律の事を知る聡明な方でした。だからこそ、戒律(ルール)に固執することもなく、師の指導の真意をくみ取ろうすることを、心がけていました。

賢い方だったのですね。

はい。誰もが言いにくい場面でも、自ら一歩踏み出して意見を述べる人でした。しかし、それは決して自己陶酔しないよう、よく自己を見つめ、物事を見つめていた。そこから生まれる見解でした。
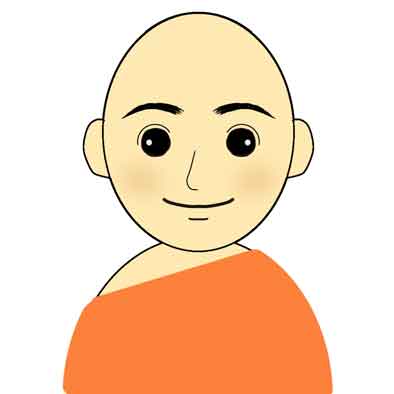
師匠はその方達のことよくご存じだったのですね。

よく、その人の話を聞くと、どっちが優れているかなんて、決めつけられないですね。

その時その場のありのままの事を知らない人が、その二人の違いを知る事はできません。違いはあっても共に立派な方達でしたよ。

ですから、人と人を比べて、優劣をつけ、数字の上で評価するにように推し量ることは止めたほうがよいです。

はい。

人をこのように計れば、その考え方に病んでくるでしょう。自分も他者からのそのような評価を気にし、その考え方に患わされることになるでしょう。
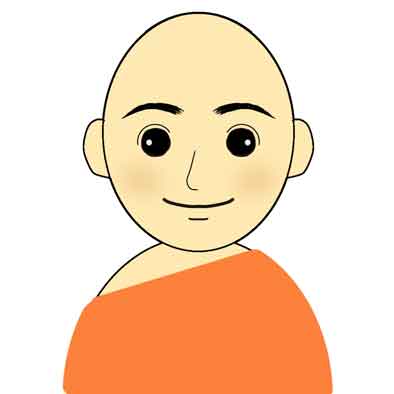
勉強になります。

ありがとうございました。
補足情報
出典
-
- 雑阿含経巻第35-990
(九九〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢。詣舍衞城次第乞食。至鹿住優婆夷舍。鹿住優婆夷遙見尊者阿難。疾敷床座。白言。尊者阿難令坐。時鹿住優婆夷稽首禮阿難足。退住一面。白尊者阿雖。云何言世尊知法。我父富蘭那先修梵行。離欲清淨不著香花。遠諸凡鄙。叔父梨師達多不修梵行。然其知足。二倶命終。而今世尊倶記。二人同生一趣。同一受生。同於後世得斯陀含。生兜率天。一來世間究竟苦邊。云何阿難。修梵行。不修梵行。同生一趣。同一受生。同其後世。阿難答言。姊妹汝今且停。汝不能知衆生世間根之差別。如來悉知衆生世間根之優劣。如是説已從坐起去。時尊者阿難還精舍。擧衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足退坐一面。以鹿住優婆夷所説廣白世尊。佛告阿難。彼鹿住優婆夷云何能知衆生世間根之優劣。阿難。如來悉知衆生世間根之優劣。阿難。或有一犯戒。彼於心解脱慧解脱。不如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。或有一犯戒。於心解脱。慧解脱。如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。於彼籌量者言。此亦有如是法。彼亦有是法。此則應倶同生一趣。同一受生。同一後世。彼如是籌量者。得長夜非義饒益苦。阿難。彼犯戒者。於心解脱。慧解脱。不如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。當知此人是退。非勝進。我説彼人爲退分。阿難。有犯戒。彼於心解脱。慧解脱。如實知。彼於所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。當知是人勝進不退。我説彼人爲勝進分。自非如來。此二有間。誰能悉知。是故阿難。莫籌量人人而取。人善籌量人人而病。人籌量人人。自招其患。唯有如來。能知人耳。如二犯戒二持戒亦如是。彼於心解脱。慧解脱。不如實知。彼所起持戒。無餘滅。若掉動者。彼於心解脱。慧解脱。不如實知。彼所起掉無餘滅。彼若瞋恨者。彼於心解脱。慧解脱。不如實知。彼所起瞋恨無餘滅。若苦貪者。彼於心解脱。慧解脱。如實知。彼所起苦貪無餘滅。穢汚清淨。如上説。乃至如來能知人人。阿難。鹿住優婆夷。愚癡少智。而於如來一向説法。心生狐疑。云何阿難。如來所説。豈有二耶。阿難白佛。不也世尊。佛告阿難。善哉善哉。如來説法若有二者。無有是處。阿難。若富蘭那持戒梨師達多亦同持戒者。所生之趣。富蘭那所不能知。梨師達多爲生何趣。云何受生。云何後世。若梨師達多所成就智。富蘭那亦成就此智者。梨師達多亦不能知彼富蘭那當生何趣。云何受生。後世云何。阿難。彼富蘭那持戒勝。梨師達多智慧勝。彼倶命終。我説二人同生一趣。同一受生。後世亦同是斯陀含。生兜率天。一來生此究竟苦邊。彼二有間。自非如來誰能得知。是故阿難。莫量人人。量人人者自生損減。唯有如來能知人耳。佛説此經已。尊者阿難聞佛所説。歡喜奉行
(大正No.99, 2巻257頁b段26行 – 258頁a段26行)
- 国訳一切経阿含部3巻10頁




コメント