無記(記していない)
お釈迦さんはあえてそのことについて答えない。お経の中にその答えは記されていない。
そういうのを仏教学では「無記」と言います。この教えは、経典の随所で見られます。今回の話もその無記を表す一つの例です。


無記について有名な説法は上記の二つ、特に上の「毒矢のたとえ」はよく知られている話です。
基本的に仏教を理解する上で役に立たない、あるいは余計な混乱をもたらす。そんな場合は敢えて何もしゃべらないのが、お釈迦さんのスタイルです。
これは何も本当にわからないわけではなく、知識の使い方が誤った方向に進んでいることを諭す意味合いが大きかったのではないかと思います。
私達人間は同じものでも全然違ったものの見方をします。

誰かとしゃべるときもそうです。同じ空間を共有していても、相手には自分の顔が見え、自分には相手の顔がみえる。そしてそれは互いに視覚として認識できません。でも同じ時間と空間を共有しているわけです。
本来はそういうあり方を理解することに努めなさいというのが、お釈迦さんの伝えたいことだったと思われるのです。
しかし、私達はどちらが正しいか間違っているか、分けらないものをはっきりさせようとしてしまいます。特に真面目で真剣になればなる人ほど、その傾向が強いように私は思います。
私自身も他人事ではありません。やはり答えのわからないものをはっきりさせたいという気持ちは人一倍強いと思っています。
これは別に悪い事ではないのです。しかし悪いようにも働くことを知っておかなければなりません。
「無益の争論」と題した「仏教トーク」では、弟子達が言い争いをしている所を集めました。(他にも話があります)
イラストや声の都合上、同じ人物を使っています。しかし経典では誰が誰と争っていたかまでは明確に記されていません。「衆多の比丘」と記されています。
つまり特定の人物だけが、こういう知識を用いた争いの沼にはまってしまったわけではなく、多くの真面目で真剣な弟子達が何人も何人も、この知識を用いた争いの沼にはまったのだろうと私は考えています。
それぐらい知識というものは用い方次第で武器にもなり、争いの種になることを、知識を学ぶ人間は理解しないければならないのかもしれません。
「教え(知識)を捨てなさい」という説法があるくらいですからね。

知識や思想といったものも用い方次第では、私達を活かす道具にもなり、私達を苦しめる重荷にもなるのでしょうね。
※この記事は、下記の仏教トークのあとがきとして書きました。



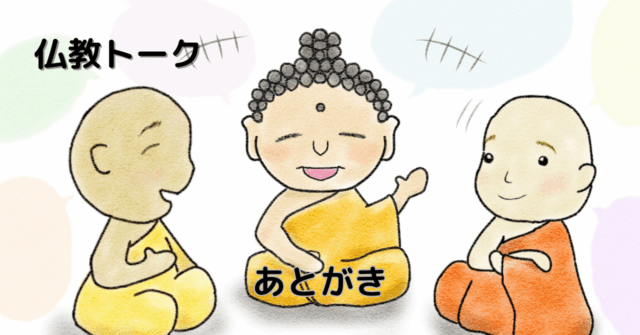

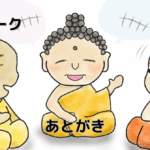
コメント