 法の種
法の種 空気:空は無でもなく、そのまんまでもない。
空気を観て
 法の種
法の種  法の種
法の種 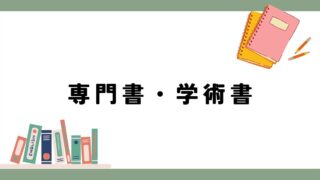 禅僧ちしょうの棚
禅僧ちしょうの棚  法の種
法の種  法の種
法の種  法の種
法の種 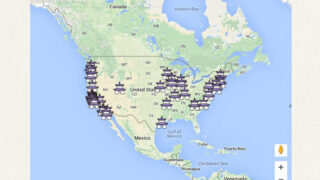 法の種
法の種  法の種
法の種 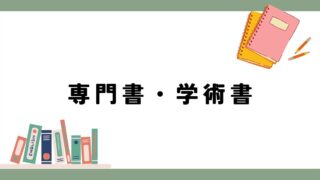 禅僧ちしょうの棚
禅僧ちしょうの棚  法の種
法の種  法の種
法の種  法の種
法の種 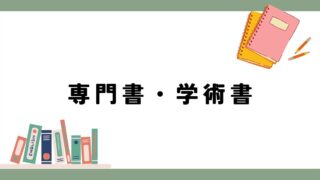 禅僧ちしょうの棚
禅僧ちしょうの棚  法の種
法の種 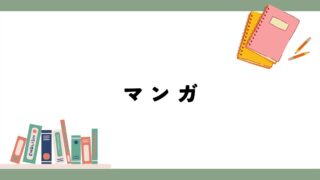 禅僧ちしょうの棚
禅僧ちしょうの棚