「業」と<業>
こちらの記事は、下記の仏教トークのあとがきとしてかきました。

古代インドの慣習としての「業」
業は仏教用語の中でもよく誤解されがちな言葉です。仏教は<業>を説きます。
今回、「業」と<業>という表記を分けました。古代インドの慣習として一般的に使われていたものを「業」とし、仏教の<業>と区別しました。
そもそも「業」という言葉は、お釈迦さんが生まれた約2500年前の古代インドでは、すでに一般的に使われていた言葉でした。パーリ語ではKarman(カルマ)と言います。
当時の一般常識だったといってもいいでしょうか。「業」の考え方は、カースト制度と呼ばれる身分制度や輪廻転生の思想とも大きく関連しています。
徳ある人は、(前世の)徳ある行為(業)によって生じ、悪人は悪しき行為によって生じる、というウパニシャッドの著名な哲人ヤージニャヴャルキヤの言葉は、業と輪廻のかかわりを典型的に表明する。このように業は単なる行為にとどまらず、死後にも潜在的なちからとなって残存し、人の来世の善悪のあり方を規定するとの考えは広く浸透するようになった。
岩波仏教辞典より
輪廻転生なども仏教の考え方だと誤解されている方も多いですが、これらはバラモン教の思想が広く知られていた古代インドの風習、古代インドの一般常識です。
もちろん、当時これら世間一般に説かれる考え方に納得がいかなかった人物もいました。お釈迦さんも、そんな当時の常識に疑問を持ったうちの一人でした。
仏教では<業>=習慣という意味になる
それを端的に表すものとしてこんなお釈迦さんの言葉があります。
「生まれによってきまるのではく、行為によってきまる」
これは法句経の一説でお釈迦さんが説いているものです。もちろん、この行為とは、今私達が自分自身で行う行為のことを意味します。
前世の行い「業」が今の生き方に影響するという考え方を、今この時の自分の行い<業>によって今の生き方に影響するという考え方に変容させたのです。
当時の常識であった「業」という風習・慣習を、今の自分の行いや習慣が<業>であると言い換えたと言えば、わかりやすいでしょうか?
日本語でも慣習と習慣と似たような字になってしまいますが、おそらく当時でもこれぐらいの変化だったのだろうと思います。しかし、意味が大きく異なります。
こういった時代背景の理解も、仏教を理解する上では役に立つことではないでしょうか。
ちなみに、当時から輪廻思想(前世や死後)についての質問をお釈迦さんにする人はいましたが、お釈迦さんは無記(答えない)ことでその応えとしています。




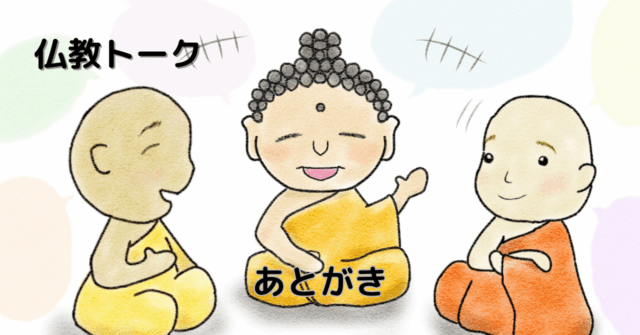

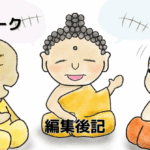
コメント